2025.05.15
採用ブランディングとは? 具体的な方法と進め方のポイント
- #ブランディング
- #採用
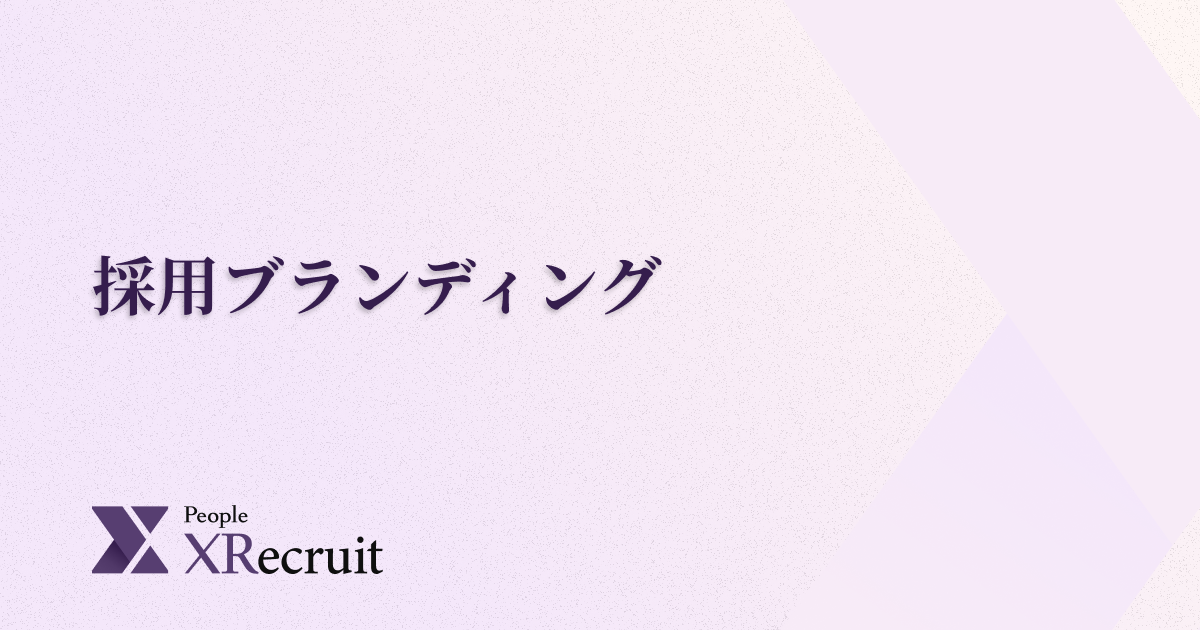
人材の流動性が高まる中、長期に活躍できる人材を確保する手法として、採用ブランディングが注目されています。
採用ブランディングには採用数確保だけでなく早期離職の防止も期待できますが、ポイントを押さえて運用を行わなければ、十分な効果を発揮しません。
この記事では、採用ブランディングの概要やメリット、デメリットのほか、成功させるためのポイントについても解説します。
採用ブランディングとは
採用ブランディングとは、求職者をターゲットとして就職先としての魅力を伝える活動全般です。一般的なブランディングは、消費者をターゲットとして行われ、商品やサービスの訴求力を高めます。一方、採用ブランディングは、人材採用領域に特化して行われるのが特徴です。
また採用ブランディングでは、企業自体への信頼感や好感度を醸成することで、求職者の応募意欲・入社意欲を向上させます。そのため一時的な広告出稿などではなく、長期間かつ継続的な活動が必要です。
採用ブランディングのターゲットには、すでに自社に興味を持っている求職者だけではなく、潜在的な求職者も含みます。そのため、採用ブランディングには待遇や福利厚生といった採用に直接関わりのある内容だけでなく、企業のビジョンや社内風土も含めることが必要です。
採用ブランディングの目的
自社の価値観にマッチする人材の採用が、採用ブランディングの目的です。高いスキルを保有しているなど優秀であるだけでなく、ビジョンや文化に共感し長期に活躍できる人材の確保を目指します。
企業文化に共感して入社した人材はエンゲージメントも高く、単に義務として業務を行う人材よりも高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。定着率も高いため、長期にわたって自社での活躍が期待できます。
採用広報や採用マーケティングとの違い
採用活動における企業の取り組みとしては、採用ブランディングのほかに採用広報や採用マーケティングが挙げられますが、それぞれ以下のような特徴を持ちます。
採用広報は、企業が採用時に行う広報活動であり、企業の認知度向上を目的とした活動です。採用ブランディングと異なり、自社のブランディングまでは行いません。
採用広報で発信する情報は企業の採用情報が中心です。また活動が活発になる時期も限定的で、新卒採用向けであれば学生からの応募が集中する時期、中途採用であれば募集をかけるタイミングで採用広報は行われます。
採用ブランディングが長期的な企業全体のブランディングを通じて求職者に自社をアピールする活動であるのに対し、採用広報は採用活動に直結する活動といえるでしょう。
採用マーケティングは、マーケティング手法をベースとした求職者へのアプローチです。より効率的に、必要な人材を応募・採用へつなげることを目的とします。
採用マーケティングではターゲットをピンポイントに絞り、広告やスカウトメールなどで必要な人材に自社への応募を訴求します。広告のPV数やスカウト返信率など、施策に対する短期的かつ具体的な数値目標を設定する点も採用マーケティングの特徴です。
採用ブランディングが注目される背景
採用ブランディングが注目される背景には、人材獲得競争の激化とSNSの普及があります。
少子高齢化による母数の減少だけでなく、急速に変化する社会や市場ニーズ、労働に関する価値観の変化も人材不足の要因です。業種・職種・事業規模を問わず、多くの企業で人材確保が難しく、同時に優秀な人材の流出防止が課題となっています。
またSNSの普及により、在職者や消費者など企業以外から発信される情報を、求職者は容易に得られるようになりました。待遇や職場環境といった働く場としての情報だけでなく、企業やサービスへの評価を日常的に目にすることで企業への好感度や親しみやすさが左右され、職場選びにも影響を及ぼしています。
こうした状況の中、求職者は労働環境や企業の価値観、企業への好感度など、さまざまな情報を総合的に判断して就業先を選ぶようになりました。定着率の高い優秀な人材を獲得するための手段として、採用ブランディングが注目されています。
採用ブランディングのメリットとデメリット
採用ブランディングには、採用コストの削減と離職率の低下というメリットがあります。
採用ブランディングによって企業の認知度が向上し、応募が集まりやすくなります。そのため、認知度の低い状態で採用活動を行うよりも、効率よく母集団を形成することが可能となります。
ビジョンや企業風土に共感した人材の応募や採用にもつながるため、採用ミスマッチが減り、早期退職も防げます。採用ブランディングは従業員エンゲージメントにも良い影響が出るため、人材の流出防止も期待できるでしょう。
他方、採用ブランディングには、手間がかかる割に効果が見えるまでに時間がかかるというデメリットもあります。
採用マーケティングや採用広報と異なり、採用ブランディングでは長期的なブランドイメージ向上を図ります。長期間にわたって企業として一貫したメッセージを発信し続けるためには、人事担当者だけでなく経営層から現場スタッフまで社内全体での取り組みが必要です。
しかし、多くの人と協力して取り組んでも、すぐに採用数向上や離職率低下という見えやすい結果につながるわけではありません。採用ブランディングに取り組む際は、効果を得るには時間がかかることも理解した上で、関係者のモチベーション維持に留意することも必要でしょう。
採用ブランディングの進め方と成功のためのポイント
採用ブランディングは、やみくもに進めても効果が出ません。実際に活動を始める前の準備を綿密に行い、実行後は検証と改善を繰り返すことが重要です。
採用ブランディングの進め方と成功のポイントについて、以下のステップごとに解説します。
- 自社分析
- 採用ターゲットの明確化
- 運用計画の策定
- 社内通知と計画実行
- 計画の見直しと改善
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社分析
まずは自社の強みや課題などを分析し、競合他社と比較します。その上で、求職者に向けて訴求すべきポイントを明確にしましょう。
採用ブランディングにおける自社分析では、KJ法・3C分析・SWOT分析など、マーケティング分析のフレームワークを活用します。待遇や社風など採用活動に直接関わる事柄を中心にしつつ、商品やサービスなど自社に関することも分析対象に盛り込むのがポイントです。
自社分析では、客観的かつ事実に基づく分析が求められます。理想像ではなく、現段階の事実を分析することが、採用ブランディングの方向性を正しく設定する第一歩です。
分析が完了したら、求職者へ訴求するポイントを選定します。ポイントを絞ることで活動の軸が定まり、求職者に自社の魅力をより強く印象づけられるでしょう。
採用ターゲットの明確化
次に、自社が採用したいターゲットを、具体的かつ明確にします。採用ターゲットを詳細に設定することで、伝えるべきメッセージや伝えるための手段が明らかになるでしょう。
たとえば、「個人での目標達成意欲が強い人」と「チームワークを重視し、チームとして成果獲得を目指す人」の心に響くメッセージは、同じではありません。またターゲットが普段よく目にしているメディアやSNSが何であるかによって、効果的な広告出稿媒体も変わります。
年齢や経験、キャリア志向だけでなく、性格や人となりなどにも踏み込んで設定していきましょう。ターゲットを明確にすることで、長期にわたる採用ブランディングでも一貫したメッセージの発信を実現します。
運用計画の策定
次に、ターゲットに合わせた運用計画を策定します。
求職者に向けて伝える内容や採用コンセプト、インタビュー動画などに登場してもらう社員、発信チャネルの選定など、具体的な計画を立てていきましょう。あくまでも、ターゲットに合わせた内容にすることが重要です。どれほど魅力的な言葉や内容であっても、ターゲットに響く内容でなければ意味がありません。
また、運用計画は、自社の採用サイトやSNS、求人サイトなど、採用に関わるすべてのチャネルで統一することが大切です。どのチャネルでも統一的なブランディングとすることで、必要な人材への訴求力が高まるでしょう。
社内通知と計画実行
運用計画が固まったら、内容を社内で共有した上で計画を実行します。
採用ブランディングは、人事担当者の取り組みだけでは成功しません。チャネルに掲載する記事や動画、業務風景写真などの作成には、経営者や現場の協力が不可欠です。社内全体で採用ブランディングの活動を共有し、全員で取り組むことが求められます。
担当者が交替しても変わらぬ運用ができるよう、マニュアルを作成しておくとよいでしょう。採用ブランディングは年単位での活動であり、その間にメンバーが異動したり退職したりする可能性もあります。そのような事態に備えてあらかじめ準備をしておくと、滞りなく一貫した活動を続けることが可能です。
計画の見直しと改善
実際の運用が始まったら、定期的に採用活動の結果を振り返り、改善を行いましょう。チャネルごとのインプレッション数やコンバージョン数など定量的な数値のほか、ブランドイメージなど定性的なデータもアンケート調査を通じて検証します。もし想定していた効果が出ていない場合は施策を再検討します。
採用ブランディングは、結果が出るまでに長い時間を要するものです。臨機応変に計画を見直す柔軟性と目指すターゲットの一貫性を両立させることが、企業のブランドイメージの育成と確立につながります。
採用ブランディングの発信チャネル
採用ブランディングで利用できるチャネルとしては、以下のものが考えられます。
- 自社の採用サイト
- SNS
- 求人サイト
- イベントやセミナー
それぞれ特徴やメリットが異なるため、ターゲットに合わせて複数のチャネルを活用しましょう。
自社の採用サイト
自社の採用サイトは、採用ブランディングにおいてまず力を入れるべきチャネルです。他のチャネルでは得られない情報を充実させましょう。
福利厚生やキャリアパス、研修制度、社員インタビューなどを掲載するにあたっては、求職者が具体的に働くイメージを持てるものにすることが重要です。たとえば社員インタビューでは、ターゲットとする人材に近い年齢やライフステージにある社員に登場してもらうとよいでしょう。
採用サイトは自由度が高く、デザインやサイト構成など情報の見せ方でも企業のイメージ向上を図ることができます。「作って終わり」ではなく、採用ブログで社内イベントの様子を紹介するなど、タイムリーな情報更新が信用につながります。
SNS
SNSは採用サイトよりもタイムリーに情報を発信できるチャネルです。短い動画や写真など簡易なコンテンツでも発信が可能で、特に、若年層をターゲットとした採用ブランディングで効果を発揮します。
SNSのメリットは、求職者と直接コミュニケーションが取りやすい点です。親近感を持ってもらいやすく、拡散力も強いため、潜在的な求職者層における認知度向上にもつながります。
SNSを採用ブランディングに活用する際には、ターゲットに応じたツールを選ぶことが重要です。
たとえば20代では、8割近くがX(旧Twitter)やInstagramを利用しています。しかし、Facebookの利用率はは3割弱です。若年層を採用ターゲットとする場合は、XやInstagramにリソースを割くことで、効率的な訴求が期待できるでしょう。
参照:総務省情報通信政策研究所|令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>(令和5年6月)
求人サイト
求人サイトは、新卒・中途採用ともに幅広く活用されています。スカウト特化型やハイクラス専門など、特徴やターゲットを絞ったサイトも増えているため、自社の採用ブランディングの方針に合ったサイトを選ぶことが重要です。
求人サイトのメリットは、実際に求職活動を行っている人にダイレクトに情報を発信できる点でしょう。転職意欲や就業意欲が高い人に効率的に情報を届けられるため、早期に結果につながりやすく、また応募数などKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)も立てやすいチャネルといえます。
反面、決まったテンプレート内での情報発信となるため、内容が他社と似通いやすく、自社の魅力を伝えにくい点はデメリットです。社員紹介記事や動画を利用して具体的なイメージを伝えるとともに、スカウトメールの活用などターゲットに合わせた工夫が求められます。
イベントやセミナー
転職イベントや企業説明会など、求職者と直接コミュニケーションをとれる機会は、相手に印象を残しやすく、自社の魅力を伝えるのに効果的です。求職者からの質問にもその場で回答できるため、自社への理解を深めてもらいやすいでしょう。
採用を目的としないセミナーや勉強会も、自社の社員が発表者として登壇することで知名度向上につながります。専門性の高い職種であれば自社のアピールにもつながり、成長意欲の高い求職者に訴求できるでしょう。
イベントやセミナーは主にリアルタイムでのやりとりとなるため、良い印象を与えやすい反面、悪い印象も残りやすくなります。参加社員は慎重に選び、内容や方針について事前に細かい打合せをしておくことが重要です。
まとめ
採用ブランディングは、潜在層を含む幅広い求職者に対して企業イメージの向上を図る活動です。自社の社風にマッチした人材確保につながるため、早期退職を防ぎ、長期的な採用コストの抑制が期待できます。
ただし、採用ブランディングはすぐに結果が出るものではありません。訴求ポイントや採用ターゲットは保持しつつ、発信方法や見せ方を柔軟に改善することが、採用ブランディング成功の鍵になるでしょう。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。

