2025.05.07
AI採用とは?採用業務においてAIを活用する具体的な場面やメリット、留意点を解説
- #AI面接
- #採用
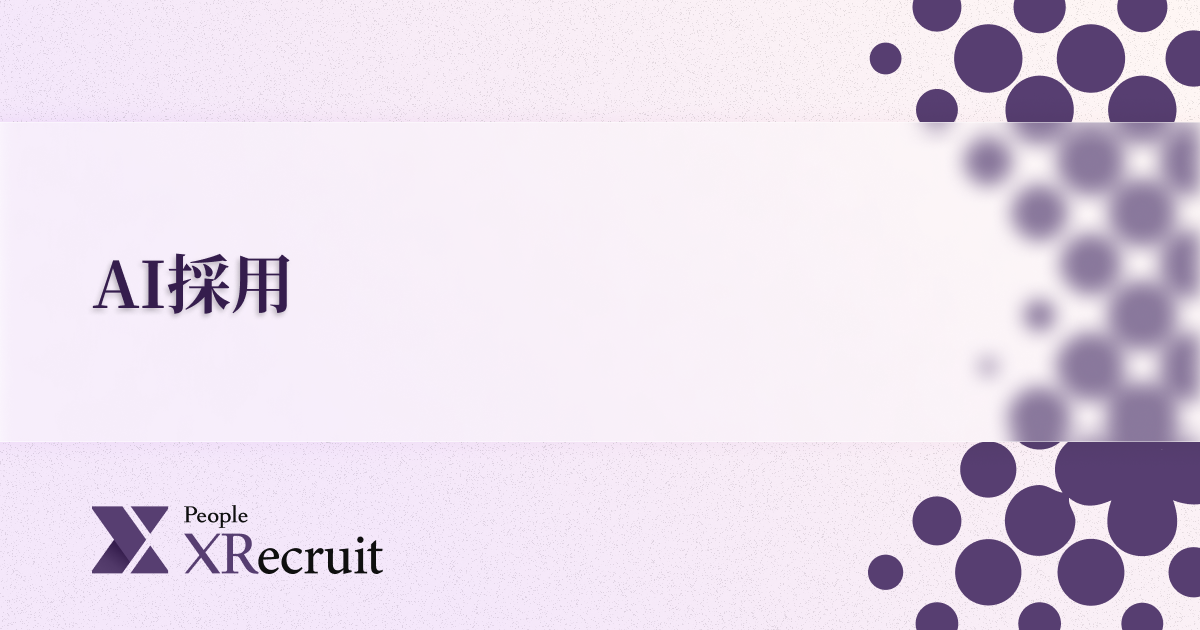
AI(人工知能)はビジネスシーンにおいてもさまざまに利用されるようになっており、採用活動も例外ではありません。採用活動には多くの業務が含まれますが、AIを活用することで、その負担軽減や精度向上、公平性の確保などが図られています。
この記事では、主に企業の人事・採用担当者へ向けて、具体的に採用業務のどのような場面でAIを活用しうるのか、また、活用する場合のメリットや留意点、導入ステップについて解説します。
AI採用とは
AI採用の概要
近年、採用活動においてAIを活用するケースが増えており、そのような採用活動を指して「AI採用」と言われるようになっています。AIを活用することで、大量のデータを速く正確に処理することができ、AI採用では、人材獲得の精度を高めることや、採用業務を効率化することが目指されます。具体的には、求人情報の作成、応募者の絞り込み、書類選考での評価、さらに、面接の実施、といった場面での活用が広がっています。
面接においてAIを活用する「AI面接」については、より詳しい内容を下記の記事にまとめていますので、あわせてお読みください。
AI面接とは? メリットや導入時の注意点・ポイントを詳しく解説
注意したいのは、採用業務のすべて、特に採否の判断までをもAIに行わせるわけではないという点です。データ処理など、AIに委ねたほうが効率的で、またそうすることに問題のない作業もありますが、採用業務の中には、人にしかできない、または、人が行うべき作業もあります。あくまで、人が行う採用業務をサポートする一つのツールとしてのAI活用と捉えるのが適切です。
AI採用が広がる背景
労働人口減少に伴い人材獲得競争が激化する中で、各企業にとって、自社に必要な人材を高い精度で獲得することが大きな課題となっており、応募者のスキルや適性、自社への適合度合いについて、データに基づいて客観的に判断することの重要性が増しています。また、採用活動の長期化や中途採用の拡大といった状況から、採用担当者の業務負担が増加しており、この軽減も課題となっています。
その中で、近年、AI技術の発展により、AIに任せられるタスクの内容や範囲が広がってきています。採用活動においても、AIを活用することで、採用担当者は自らが担う業務の量や時間を削減しながら従来以上に高度な分析や判断を行うことができ、採用の精度向上、業務効率化による負担軽減などを実現することが可能となってきているのです。さらには、スピード感を持った採用活動や、リソースの再配分による企業のアピール・魅力づけへの注力といったことも可能となり、より優秀な人材の獲得の一助となることも期待されます。
採用業務におけるAIの活用場面
採用業務においてAIの活用が進んでいる具体的な場面としては、以下のものがあります。
求人情報の作成
文章の生成が可能なAIツールを、求人情報の文面の作成に活用することが可能です。自社の特徴や、必要とする人材要件につき、少ない労力でクオリティの高い文章を作成することができます。また、社員のインタビューといった採用サイトに掲載するコンテンツの作成にAIを用いることも考えられるでしょう。
候補者の探索(AIソーシング)
採用候補となる人材を企業自ら探し出しアプローチする「採用ソーシング」にもAIが有効です。求人媒体のデータベースやLinkedIn、FacebookなどのSNSを分析し、適切なスキルや経歴を持つ人材を見つけるにあたり、AIを活用することで、人による工数を大幅に削減し、より効率的かつ正確に分析結果を得ることができます。また、候補者へのスカウトやオファーの文章を作成する際も、AIを用いて個々人に最適な内容とするといったことも可能です。
候補者とのマッチング(AIマッチング)
採用においては、候補者と自社とのマッチング率も重要です。候補者のスキルや経験、志向と人材要件との適合度合いが強ければ強いほどよく、入社後の活躍や定着も期待できます。しかし、特に候補者が多い場合、人がこの判断を行うには多大な労力を要します。また、人のみの判断では、主観や意図しない揺らぎが介在してしまう可能性が拭えません。AIを活用した分析を行うことにより、容易かつ迅速に、また公平に、判断を進めることができます。
候補者データベース管理
候補者に関する情報を蓄積するデータベース(タレントプール)の管理にAIを活用すると、情報の更新要否のチェック、最新の求人に適した候補者の抽出といった作業を容易に行うことが可能となります。タレントプールにどのようなデータを蓄積していくかは各企業次第ですが、退職者(アルムナイ)、以前に内定辞退となった候補者、自社の説明会等に参加した人など、さまざまな人材が含まれる場合は特に、AIを活用することで効率性が大きく増すでしょう。
チャットボット
AIを活用した自動会話プログラム「チャットボット」は、カスタマーサポートやマーケティングなど、さまざまに活用されていますが、応募者向けに用いることも考えられます。応募者からの質問や日程調整に時間を問わず対応できる仕組みを整えておくと、応募者体験の維持・向上につながります。また、たとえば、応募職種、スキルや経験などについてチャットボットでやりとりをし、その回答をデータベースに集約していくといった仕組みを構築しておくと、その後の選考作業を効率的に進めることが可能となるでしょう。
ソーシャルメディア分析
Web上の記事やSNSに掲載・投稿された内容を分析することで、求職者が抱く自社のイメージ、採用市場の動向などに関する情報を幅広く収集・把握することができます。また、候補者が問題のある発言や行動をしていないかどうかを確認する、いわゆる「SNSチェック」を行う企業もあるでしょう。いずれの場合も、AIを用いることで迅速に大量のデータを分析・検証することができます。
選考スケジュール管理
選考過程においては、候補者、採用担当者、会議室などの状況を確認しスケジュール調整をする必要が多数生じます。AIを活用した仕組みを用いると、適切なスケジュールの作成や関係者への連絡が自動でなされ、手間の軽減やミスの防止につなげることが可能です。
書類選考(AIスクリーニング)
応募者全員のエントリーシートや履歴書、職務経歴書を一つひとつ確認するのには、大変な時間と労力がかかります。AIを活用することで、データベースへの入力といった単純作業はもちろん、応募者のスキルや経験、特性、志望動機などを分析し、自社の人材要件に適した候補者を絞り込むといった過程を、負担や担当者ごとのばらつきを抑えつつ迅速に行うことが可能となります。
適性検査・性格診断
適性検査・性格診断についてもAIを搭載したサービスが登場しています。適性検査・性格診断は、候補者の価値観やコミュニケーションの特性、潜在的な能力などを推し図ることができ、導入する企業も多くなっていますが、AIを用いることで、迅速に、より高度かつ客観的な検査・診断結果を得ることができます。現有社員の検査・診断結果と合わせて分析することで、活躍が見込めるかどうか、どの部署への配置が最適か、といった判断に役立てることも可能です。
AI面接
AIを活用した面接サービスもさまざま登場しています。一般的な仕組みは、応募者がオンライン上で、事前に用意された質問に答え、その様子を録画するというものです。対話型AI技術の進歩により、一問一答形式ではなく、応募者の回答を受けた「深掘り質問」が可能なサービスも存在します。録画データをもとに、応募者の回答内容についてAIが分析を行い、企業はその結果を用いて採否の判断を行うことができます。コストや負担の削減、公平な面接の実施といったメリットがあることから、注目が高まっています。
「AI面接」について、より詳しい内容は下記の記事をお読みください。
AI面接とは? メリットや導入時の注意点・ポイントを詳しく解説
採用業務でAIを活用するメリット
採用業務でのAIの活用には、以下のメリットがあります。
- 工数削減・負担軽減が可能となる
- 公平な評価につなげられる
- 採用業務の精度を高められる
工数削減・負担軽減が可能となる
たとえばエントリーシートを確認し候補者を絞り込む過程をすべて人が行うのは大変な負担です。特に応募者が数百人、数千人単位となる企業では、それだけで多大な労力を要します。
大量のデータ入力・処理をAIに任せることで、人事担当者の工数を削減し負担を軽減することが可能です。これにより、担当者は、単純作業に忙殺されることなく、人にしかできない判断や意思決定といった、より重要な業務に多くの時間を充てることが可能となります。
公平な評価につなげられる
候補者の評価を複数人で分担する場合、人によって評価の異なりが生じることは避けられません。しかし、AIがすべての候補者の情報を同じアルゴリズムのもとで扱うと、一貫性のある結果を得ることができます。バイアスや主観が混ざるといったこともなく、公平・客観的にデータを判断していくことにつなげられます。
採用業務の精度を高められる
AIの活用には、ヒューマンエラーの低減というメリットもあります。大きな間違いを防ぐというだけでなく、人の目が届きづらかった点もカバーされるという利点もあるといえ、精度高く採用業務を進めることが可能となります。自社に適した人材かどうかを見極める際にAIを用いる場合、人材要件はもちろん、現有社員の評価データなどもシステムに組み込んでおくと、さらに精度の高い判断を実現できるでしょう。
採用業務でAIを活用する際に留意したい点
採用業務におけるAIの活用には、メリットもある反面、気をつけたい点も存在します。以下の点に十分留意しましょう。
- データの取扱いに最大限注意する
- AIの限界も踏まえた運用を行う
- 丁寧かつ明確な体制をとる
データの取扱いに最大限注意する
文章の生成などにAIを用いる場合、出力された内容について、正確性や適切性が担保されているかどうか、著作権侵害となっていないかどうか、といった点を十分に確認することが必要です。
個人情報も厳正に取り扱わなければなりません。漏洩や不正利用が生じないようセキュリティ対策を徹底することはもちろんのこと、AIを用いることで、プライバシー侵害を起こしてしまったり、収集すべきでない個人情報を意図せず収集してしまったといった事態に陥らないよう十分に注意しましょう(個人情報保護法20条2項、職業安定法5条の5)。また、個人データの第三者への提供は法律で制限されていますが(個人情報保護法27条)、AIにデータを渡す際などにこの制限に抵触しないかどうかといった確認や、AI利用時に入力したデータがAIの学習用データとして使われない設定をするといった管理も大切です。
さらに、AIに関してはすでに「人間中心のAI社会原則」「AI事業者ガイドライン」が出されているほか、2025年の通常国会で、いわゆる「AI法」(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)の法案が提出されています。今後ますます、国内の法整備や、自主規制、ガイドラインに関する動きを注視していく必要があるといえます。
参照:統合イノベーション戦略推進会議決定「人間中心のAI社会原則」(平成31年3月29日)
参照:総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」(令和7年3⽉28⽇)
AIの限界も踏まえた運用を行う
AIは、事前に備えられた学習データやアルゴリズムに基づいて処理を行い、結果を出力します。そのため、データが不十分であったり偏りがあったりすると、期待した結果が得られなかったり結果に偏りが生じたりする可能性が高まります。
単純なデータの入力や調整といった業務でAIを用いる場合は、ミスの生じないような設定をしておくことで問題が起きることは考えづらくなりますが、評価に関係する場面では特に注意が必要です。たとえば、評価の前提となる学習済みのデータが、男性のものに偏っている、特定の大学の出身者は平均的に業績が良いという傾向が出ている、というものであった場合、男性やその大学の出身者が高い評価を受け、そうでない人は個人の能力が高いとしても不利な評価を受けてしまうといったことが起こりえます(統計的差別と言われる問題です)。
また、AIの処理には、客観性・統一性といった利点がある反面、柔軟な対応が難しく画一的な評価となってしまいかねないという側面もあります。少なくとも現在においては、数値化・言語化が難しい要素の評価や、多様性の尊重は得意であるとは言いづらく、AIを活用しながらも最終的には人により判断がなされることが重要だと言えます。
丁寧かつ明確な体制をとる
採用におけるAIの活用には、時間短縮や公平性の向上など、企業・応募者双方にメリットがあるものの、自らの情報がどのように扱われるかや、どのような判断がなされるかがわからず、自身の採否の判断にAIが介在することに対して抵抗感を抱く人が存在することも考えられます。
応募者の不安を払拭するには、どのような目的でどの部分にAIを活用しているのか、わかりやすく丁寧に説明できる状況としておくことが求められます。そのためには、人とAIの役割分担を明確にしておく必要があります。またその際、あくまでAIはサポートツールであり、最終判断や関係構築など、人が行うべき業務は人が行うという姿勢を持つことが大切です。AIの活用による効率化で人の稼働時間を捻出し、応募者とのコミュニケーションにより多くの時間を充てることも有意義です。定期的な検証・見直しを行うことも、安全・適切な運用の実現におけるポイントであるといえ、こうした総合的な取り組みにより、懸念の低減につなげていくことができるでしょう。
採用業務にAIを導入する際のステップ
最後に、AIの導入にあたって採るべきステップを確認しておきます。
AIの活用方針を決める
まず、自社の採用フロー全体を確認し、どの段階にどのような課題や改善の余地があるのかを把握しましょう。その上で、課題解決や改善のために、AIに何を任せることができるかを検討します。その際、AIの得意領域と留意事項、人が担うべき領域を十分に考慮に入れ、フロー全体の中に適切に組み込むことが大切です。フロー全体の中でAIを活用する場面、その目的、運用体制を具体化することで、どのようなシステム・ツールが必要かも明確になり、運用開始後もより高い効果を得られると考えられます。
システム・ツールの選定
AIを活用することが決まったら、実際に用いるシステムやツールを選定します。その際、特に以下の点を確認するとよいでしょう。
- 自社の方針や目的に沿ったものであるか(課題解決につながるか)
- 信頼性・透明性
- セキュリティ対策
- 操作性・使いやすさ
- 他のシステムとの連携可否
- 費用・価格形態
実施、改善
システム・ツールの導入後は、実際の運用と改善のプロセスに入ります。運用開始時は、自社の採用基準や人事評価基準など、システムに組み込むデータがある場合、その用意も事前に行っておく必要があります。運用が一定程度進んだ後は、AIの活用により所期の目的を達成することができたかどうかを検証し、データの追加やアップデートの必要性なども含め、必要な見直しを継続的に行っていきましょう。
まとめ
AIの技術発展は目覚ましく、活用可能な範囲や将来的な可能性も広がる一方です。採用業務においてもAIを活用することで、負担軽減や精度向上、公平性の確保といったメリットを得られるでしょう。ただ、AIの活用にあたっては、個人情報等の適切な取扱いの徹底、AIの特徴や限界も理解した上での活用・体制整備なども必要です。メリットの最大化を図りながらも、あくまで人が判断を行う上でのサポートツールであるという意識のもとで、適切に運用していきましょう。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。

